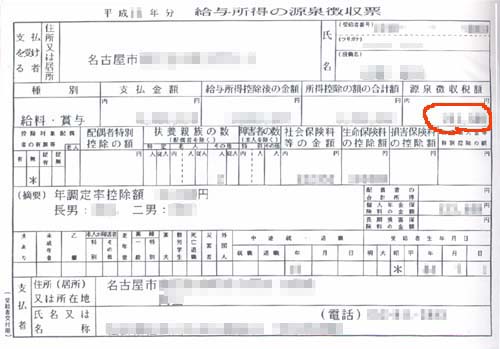
|
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
180万円以下 |
収入金額×40% 「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」 |
|
180万円超
360万円以下
|
収入金額×30% + 18万円 |
|
360万円超
660万円以下
|
収入金額×20% + 54万円 |
|
660万円超
1,000万円以下
|
収入金額×10% +120万円 |
|
1,000万円超 |
収入金額× 5% +170万円 |
|
課税される所得金額 (千円未満切捨て) |
税 率 |
控 除 額 |
|
330万円以下 |
10% |
|
|
330万円超〜 900万円以下 |
20% |
33万円 |
|
900万円超〜 1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
|
1,800万円超 |
37% |
249万円 |